
健康住宅研究所
松尾先生 特別講演「健康で快適な省エネ住宅の実現」<新築編>

教えて松尾先生!快適な省エネ住宅をつくるには?<新築編>
省エネ基準適合の義務化など、今や新築住宅を建てるときの必須条件ともいえる省エネ性能ですが、具体的にどこを重視すればいいのか、悩む方も少なくないでしょう。 今回は、「健康で快適な省エネ住宅の実現」に関する講演内容を紹介します。 講師の松尾和也先生は、松尾設計室の代表取締役を務め、今や日本における高性能住宅設計の第一人者です。高断熱高気密を基盤とした家づくりはもちろん、省エネ住宅の重要性を広めるために積極的な情報発信も行っています。 講演で述べられた、省エネ住宅を建てるときに押さえておきたいポイントを紹介します。
-
建築士 松尾 和也
株式会社松尾設計室 代表取締役 JIA登録建築家 APECアーキテクト -
松尾先生
新築住宅と幸せな生活 新築住宅を建てるとき、何にこだわるかは特に悩む部分でしょう。幸せな生活を実現するために、住宅が貢献できるのは次の4つの要素です。
- 1.暖かさ・涼しさ
- 2.美しさ
- 3.経済的
- 4.時間短縮
最近では、室温が2℃上がるだけで、将来の介護期間が4年短縮されるという研究結果も報告されています。室内の暖かさが健康の維持に関わることが立証されつつあり、住まいの暖かさは特に重視したい項目です。
さらに共働き世帯が増えた今では、「時間短縮」も欠かせません。共働き世帯に聞くと、普段の睡眠時間が4時間程度である方が非常に多く、明らかに睡眠が不足しているのがわかります。ファミリークロークや衣類乾燥機の設置など、住宅設備の工夫で家事時間を短縮し、睡眠時間を4時間から5時間に増やすことができれば、確実に健康に繋がるでしょう。

-
住まいの快適性と断熱性 住まいのどこに不満を感じるかについて、1万1,000人にアンケートを取った結果では、暑さや寒さ、そして結露に悩む人が多い事がわかりました。家の断熱性で一番弱い部分は窓で、窓を通した室内への熱の出入りは、冬の寒さの原因の約5割、夏の暑さの原因に至っては約7割にのぼります。
住まいの快適性を高めるには、断熱性を示すUA値の平均値を上げるのも大切です。しかしいくら性能の良いダウンジャケットを着ても、穴が開いていれば寒く感じるように、断熱性の低い窓は家全体の断熱性能を下げてしまいます。
断熱性と気密性、そして日当たりや風通しも考慮したパッシブデザインが取れ入れられていれば、住宅性能としては最高といえるでしょう。その上で適切な冷暖房計画を立てられるかどうかが、これから先の住宅業界では大きな課題だと捉えています。

-
未来の天気予報と住宅性能 みなさんは、環境省が提供している「2100年 未来の天気予報」というコンテンツをご存じでしょうか?地球温暖化が進んだ未来の天気予報を想定したもので、このままでは2100年には札幌で41℃、福岡では42℃になると予測されています。
あくまで未来の予測ではありますが、すでに日本の夏を安全に過ごすには、エアコンによる冷房が欠かせません。電気代の上昇に伴って冷房の費用負担が増していますが、冷房は暖房と比べて灯油やガスに分散されないため、電気代を特に高く感じやすいです。
住宅のデザインや性能は、適切な室温の維持に大きく関わります。そのため住宅を高性能化すれば、冷暖房費の負担を少なくすることも可能です。たとえば窓に庇やアウターシェードをつければ、約こたつ1台分も熱の影響を減らせます。
最近はスタイリッシュな見た目への要望から、軒の長さを短くし、黒い外壁を使用した住宅が多いですが、ぜひ室温への影響も考えてデザインを検討いただきたいです。以前、私が担当した住宅で、濃いグレーの外壁の表面温度を測定したところ、夕方の16時で表面温度は65℃。影になっている部分でも47〜8℃もあり、非常に熱を吸収しやすくなっていました。このように外壁の表面温度は色に大きく左右されますし、外壁の熱は室温にも影響します。
一方、冬でも暖まりやすい部屋にしたければ、南側の窓を大きくして日射取得率を上げるのが有効です。室温を一定に保つときに、暖房で必要となる熱負荷を「暖房負荷」と呼びます。暖房負荷の計算式は、以下の通りです。
日射取得:5割 × 断熱性:4割 × 気密性:1割「気密性:1割」と見ると、気密性の重要度は低く感じられるかもしれません。しかし暖房負荷はそれぞれの割合を掛け算しますので、気密性がゼロであれば、断熱負荷はゼロになってしまいます。このように非常に大きな意味を持つ1割だとわかれば、気密の重要性も理解しやすくなるのではないでしょうか。

-
日本の収入と幸福度の関係 現在、日本では急激なインフレが進んでいます。年収と幸福感の関係は、すでに世界各地で研究されてきたテーマです。ある程度の収入に到達するまでは幸福度も比例して上がっていくものの、ある一定レベルを超えた後は、収入が増えても幸福度は上がりません。
世界的な研究では、幸福度の折り返し点である収入額は世帯年収600万〜750万円ほど。しかし日本の場合は、およそ1,100万円だとする研究結果があります。昨今のインフレを加味すると、もう少し基準金額は上がっているかもしれません。
しかしながら、現在の日本の平均世帯年収は529万円。中央値は415万円といわれています。
このような中で生活の幸福度を上げるには、月々かかる経費を減らしていかなければなりません。考え方によっては、冷暖房費の負担を抑えることは、日常の幸せに直結するといえるのではないでしょうか。
-
省エネハウスの選び方 実際に快適な省エネハウスを建てたいと思ったら、まず住宅会社を選ばなくてはなりません。住宅会社を選ぶときの、私が考えるポイントは以下の通りです。
最低限必要な項目 推奨項目 耐震等級3 家全体の暖房・冷房計画が練られている UA値0.46以下 冬の日射取得ができている C値1以下 2級建築士以上がプランを作成している 20℃湿度50%で下枠が結露しない窓 耐久性に関する配慮がある 夏の日射遮蔽ができている モデルハウスのエアコン室外機が少ない 外断熱(鉄骨及び鉄筋コンクリート造の場合) できるだけ凹凸の少ないデザイン 面白いと感じるのが、モデルハウスのエアコン室外機についてです。総合住宅展示場の室外機の台数を見れば、その住宅会社の断熱性能と空調計画の能力がわかります。モデルハウス1棟に設置されているエアコン室外機の台数は、全国平均で7つです。これは実際に住んだときの快適さに大きく影響しますので、住宅展示場を回るときは、ぜひこのような新たな視点で各社の家づくりを比較してみてください。
また、家のデザインを考える際には暖房効率の観点から、できるだけ南面の凹凸が少ないデザインにしましょう。たとえば2つの住宅があり、同じように南側に2つの窓がある住宅でも、南側の一方が突き出た凹凸のあるデザインだと、もう一方の窓が影に入りやすくなるため十分な日射取得ができません。
凹凸の有無で暖房の省エネ効果は約7%も違います。一見暖房効率には無関係に見える家のデザインの視点からも、省エネを考えてみましょう。

-
省エネ住宅のトータルコストと性能のバランス 省エネ住宅などの高性能住宅は、断熱性や気密性の確保だけでなく、物件によっては太陽光発電や蓄電池を設置するため初期投資が必要です。しかしながら、できるだけトータルコストを抑えて夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる住宅を実現したいというのは、多くの方が望むことではないでしょうか。
高性能住宅は、今後何年住むかでトータルコストが決まります。太陽光発電は売電収入が以前よりは望めないといわれています。しかし電気代が上昇を続ける今、発電した電気を自家消費すれば、電気代が上がるほどに実質的な利益は増えるでしょう。
むやみに高性能で高価な設備を導入することによって、メンテナンスコストが高くなっては意味がありません。
長く住む新築住宅だからこそ、住宅性能とコストのバランスにこだわり、エコキュートなどメリットの多い設備を導入しながら、運用コストのバランスを取りましょう。

対談を終えて
松尾先生より、新築で快適な省エネ住宅をつくることに対する大切なポイントについてお話しいただきました。
健康住宅の家づくりを通して、高性能住宅では初期投資と運用コストのバランスを考え、トータルコストを抑えながら快適で経済的な住まいを目指しましょう。
続く後編では、今注目されている中古住宅のリフォームやリノベーションにおける高断熱リフォームの重要性についてをお届けします。
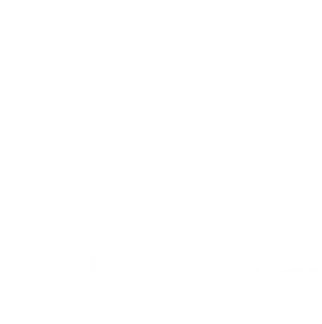
 PRIDE ~暮らしをつくる者の矜持~ vol.2-3『衛生陶器で美しい生活を届ける -TOTO取材レポ 今後の未来編』
PRIDE ~暮らしをつくる者の矜持~ vol.2-3『衛生陶器で美しい生活を届ける -TOTO取材レポ 今後の未来編』  教えて松尾先生!快適な省エネ住宅をつくるには?<リフォーム編>
教えて松尾先生!快適な省エネ住宅をつくるには?<リフォーム編>